日本が「選ばれる国」になるために:外国人材との共存を考える
- 日亜人財教育研究所
- 2024年12月24日
- 読了時間: 2分
更新日:2024年12月25日
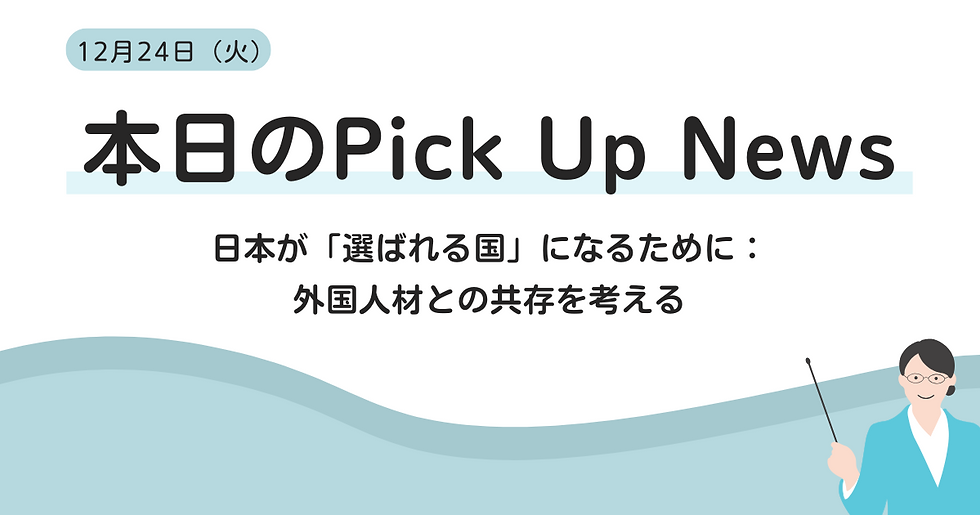
こちらの記事はダイヤモンド・オンライン「日本離れ」をどう食い止めるか(2024年12月23日)を参考に作成しています。
《概要》
少子高齢化が進む日本では、労働力人口の減少が深刻な課題です。
地方では特に人手不足が目立ち、多くの企業が外国人材の活用を進めています。
しかし、「技能実習制度」には課題が多く、円安や日本国内の労働環境の問題が相まって、
外国人材が日本を選ばなくなる「日本離れ」が進んでいるのが現状。
2023年時点で日本で働く外国人労働者は200万人を超え、
製造業やサービス業を中心に活躍していますが、適切な待遇を受けている労働者は一部に限られます。
技能実習生が多額の借金を抱えているケースや、劣悪な就労環境が問題視されています。
出入国在留管理庁の発表(24年10月)によると、
ベトナムは日本の技能実習制度における最大の送り出し国ですが、技能実習制度への悪評や、
近年の円安傾向が重なり、日本よりも賃金の高い国に人材が流れ、
24年上半期に新規入国したベトナムの技能実習生は、前年同期に比べて約2割減少。
こうした背景を受けて、日本政府は技能実習制度に代わる「育成就労制度」を2027年に導入予定ですが、詳細は未定です。
この制度が日本の労働市場にどのような変化をもたらすのか、期待と課題が交錯しています。
(ダイヤモンド・オンライン「日本離れ」をどう食い止めるか(2024年12月23日)より
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
外国人材の「日本離れ」が進んでいる現状は、日本社会全体にとって大きな課題です。
技能実習制度が外国人材にとって魅力的なものではなく、
むしろ負担やリスクを増やす存在になっているということは、日本の労働市場の競争力を低下させる一因となっています。
政府が新たに導入を予定している「育成就労制度」には期待が寄せられますが、
制度の内容だけでなく、実際の運用の透明性と公平性が確保されなければ、
根本的な解決にはつながりません。
企業や地域が積極的に外国人材を受け入れ、サポートする姿勢も重要です。
また、単に労働力として外国人材を受け入れるだけではなく、彼らが地域社会に溶け込み、
一員として生活できる環境を整えることも大切です。
多文化共生が進むことで、日本社会はさらなる活力を得ることができるでしょう。
この転換期をチャンスと捉え、制度の改革と受け入れ体制の見直しを進める必要性を強く感じました。





コメント